
|
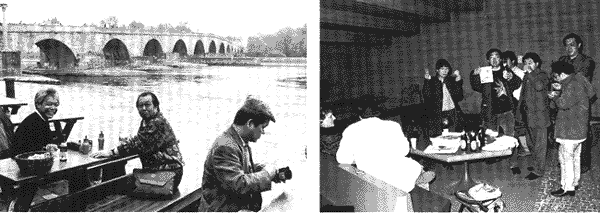
左レーゲンスブルグの風景をパック/右公演無事終了。お疲れさまのひとコマ。(レーゲンスブルク)
ズムを盛り上げる卓越したドライブで切り抜ける。 1958年、東京生まれの広上淳一が、ヨーロッパではまだそれほど、知られていない日本フィルハーモニー交響楽団の指揮にふさわしい人物だということは、なんら疑いの余地がない。と言うのも、いくらか華麗に響く名を持つこの楽団の目指すものが、少なくとも音色上、欧米のオーケストラ界でも、上級クラスに仲間人りするものとなって長期になるからである。そして事実広上は、楽団奏者の演奏水準を最善の状態にもってゆき、均質な響きのアンサンブルを築き、ますます第一級の西洋音楽に対する感受性を育てることに成功しているように思われる。もっとも、広上は彼の望むそのねらいにはまだ到達していない。なるほど彼は、この管弦樂作品で激しく動いて体にものを言わせ、マニュエル・デ・ファリャの「三角帽子」を、差し挟まれた悲劇的な音を使い、見事にセンセーショナルな作品に仕上げることに成功している、がしかし、とてもよくオーケストラを手の内に入れているにもかかわらず、何か決定的な物に欠ける。豊かな音色、リズミカルな精巧さは、まったく賛嘆すべきものである。だが、地中海的な感性と情熱のその雰囲気が十二分本当の物になっておらず、純粋な感情移入がなされないままなのである。派手な喝采フィナーレの付いたサーカスの出し物のような物である。むろん日本のオーケストラには、マニエル・デ・ファリャのイベリア人特有の語法が、実際のところかなりエキゾティックな感じを抱かせているには違いないのだが…。 ベートーヴェンの第1交響曲では広上が、なるほど正確な進行と、はっきりとした調子の進行にはマエストロとしての積極性を強烈に喚起するが、音楽の自由な息づかいには、ほんのわずかしかその余地を残Lていないという事が時折問題としてみられたが、ラフマニノフの「パガニーニ狂詩曲」では、テクニックと情緒性が高いレベルで完璧に統合されているのを経験することができた。というのもアンドレイ・ガブリーロフのピアノ技術が目下の所、再び最高のコンディションになっており、彼は、そのピアノ・パートの目標を表現豊かな極限にねらいを定め、不慣れなもものも手に余るものでも敢えて挑む一方、柔和でセンチメンタルなパートにも気高く上品なものを見出していたからである。パトス、アイロニー、そしてラフマニノフがパガニーニと超名人芸の持ち主に対する敬意として、緻密に練り上げて作った技巧による華麗な花火。そう、このソリスト・ガヴリーロフは、難なくこのオーケストラの客演を素晴らしい記憶の内に止めることができたのだった。 (クラウス・べネルト/南ドイツ新聞) 【4月30日/レーゲンスブルグ】 前日のミュンヘンから100Kmほど北にある、レーゲンスブルクという古い町での公演。ミュンヘンを離れ、速度無制限というアウトバーンに乗る頃には、あたりは大草原で、建物の影もなく、東京や大阪の都市近郊の風景とはかなり違い、国土の広さを感じさせます。 さて、その古い町レーゲンスブルクでの公演の前にトラブルは起こりました。ソリストのガーヴリーロフ氏が、ゲネプロに姿を現さなかったのです。リハーサル終了時間になっても現れません。しかもこの日は、プログラムが今までの「パガニーニ・ラプソディ」に代わって「協奏曲第2番」を初めて演奏する日で、ガヴリーロフ氏は病気のためにロンドンでのリハーサルにも来れず、まだ「協奏曲第2番」はとにかく一度も音を出していない状態でした。このままではいわゆる“ぶっつけ本番”。あまりに
前ページ 目次へ 次ページ
|

|